先生たちの前で、学校ストライキの話をしました〈みやぎ教育のつどい参加報告〉
- fffsendai
- 2021年11月19日
- 読了時間: 4分
10月30日に、「2021子どもの未来をひらくみやぎ教育のつどい 平和分科会」にFridays For Future Sendaiから池澤美月が参加しました。教職員組合に入っている先生らが多く参加するイベントです。
 |  |
私は現在、教育学部の学生で、教育に近いところにおり、教育のつどいという場で色々と話したいことがあったのでFFFf仙台から私が出ることになりました。
発表の前半は、気候変動の実態と、気候正義運動について話しました。この記事では、後半に話したことを紹介します。10/22に行った学校ストライキをふまえ、気候変動運動をしながら教育学部生をやってきた私の考えです。
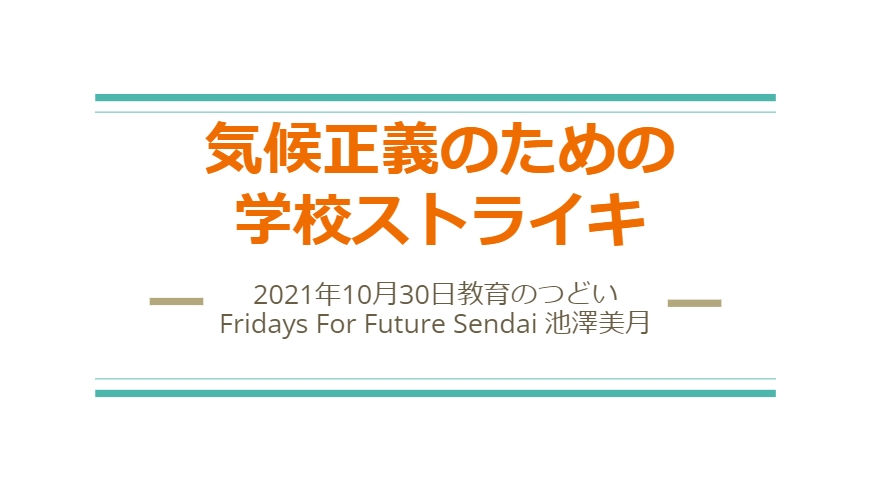
・高校生が学校ストライキしていることの意味を考えてほしい
10/22のストライキには高校生も参加しました。学校に行けば知的好奇心を満たすことができるときもあります。一見意味がないかもしれないことを楽しく勉強することは別に悪いことではないと思います。それでも、学びをストライキして、社会正義のためにアクションを起こしているのです。闘う仲間が増えるのは良いことであるが、高校生にストライキさせている現状大人はしっかりと考えなければいけないと思います。
・教えられる内容のおかしさ
バングラデシュに石炭火力発電所学校を建てているODAですが、学校では、ODAは良いものとして教えられます。途上国の支援になっていること前提で話が進みます。
学校では、日本に公害はないかのように教えられ公害を「乗り越えた」ことがアピールされます。環境アセスメント法などができ、公害が防がれているという構成になっています。ですが、丸森町のメガソーラー計画の例からも分かるように、環境アセスメントは企業活動を制御するに至っていません。しかも、国内に公害をもたらすことは減っても、グローバル・サウスに輸出されています。
公害の問題と気候変動の問題は地続きであるのにその点は度外視されています。
・問題意識をもった人たちが主体的学び、考え、議論できる場が学校にはない
アクティブラーニングのために、ディスカッションの場が設けられても、とても形式的です。しかも、公民科の学習指導要領解説に載っている議論のテーマは、「より良い排出量取引にあり方」だったりします。排出量取引は、CO2の排出量を減らさないで、どこの国から出したものにするかというやりとりのことです。排出量取引をしている場合ではなくて、今すぐCO2を減らさないといけないのです。気候危機の残酷な被害実態とすごくかけ離れていると思います。10/22のストライキでは、午後は、勾当台公園で丸くなって自分たちで学習会とディスカッションをしました。こういう場で、想像力と抵抗の知が取り戻されていくと感じます。
・未来の技術に任せておけば大丈夫、ではない
今、内閣府がSociety 5.0を示しています。これまでSociety 1.0から「進歩」してきて、これからさらに宇宙や深海に出て行って、新しい社会Society 5.0をつくろうという内容です。しかし、これまでの経済成長が良いことばかりだったのでしょうか?未来はこのまま技術で何とかできると楽観していて良いのでしょうか?
・学習指導要領「生きる力」?
貧困、性差別、競争、ブラック企業、非正規雇用、気候変動‥‥今の社会は、特に、若者を取り巻く社会は決して生きやすい社会ではありません。貧困で、グローバル・サウスで環境を破壊しながら過酷な働かされ方をしている労働者がつくった食品や衣服を買うしかない。労働時間が長すぎて学んだり自然と親しんだりできない。生きづらい社会、豊かとは言えない社会で、学習指導要領は私たちに生きる力を求めます。どうして一番にそれぞれが「生きる力」を身に付けるよう求められなければならないのか?この社会で生きていけないのは自己責任なのでしょうか?
・「中立」であることはできない
中立って何でしょうか。日本で生きる私たちにとって、中立とするものは、かなりマジョリティ寄りであり、命を脅かされることのない立場にあることを認識する必要があります。次のスライドで最後なのですが、ここで、バングラデシュ活動家からのメッセージを見てください。
こうやって闘っている人たちを前に、中立=何もしない、ということがいかに暴力的か分かるでしょう。明確に社会的に弱い立場にある人の側に立てる教員でないと、子どもにとっても社会にとっても良くないです。”社会的に弱い立場にいる人たちの側に立って、そういった弱い立場を作り出している社会を変えようと思って日々生きていく” ことを前提にしたうえで、生徒の多様な意見や行動を尊重し、一緒に考え、ときに導いていけることが大事だと思います。
内容の紹介は以上です。
教育が変われば社会が変わるとは思っていません。それにしても、今の学校、教育は、児童・生徒・学生から、現状と違う社会を想像する力を奪っていると感じます。ストライキに参加した高校生らと話をして、その想いを強くしていたところでした。
問題意識をもち、良い授業を展開している先生の発表も聞きました。学習指導要領を考えずになぞるだけの授業よりは意義がありますが、良い授業をつくっているだけでは足りないと感じました。実際に現状を変えるために、できること、するべきことがあると思います。






コメント